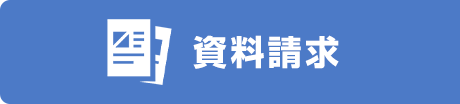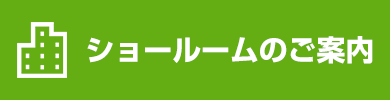通勤の時間や労力を考えるとテレワークはかなり魅力的。でも自宅は子どもが騒がしかったり、背景のきれいな場所がなかったり、かといってコワーキングスペースは1時間500円くらいでも長時間使うと料金がばかにならない。カフェは意外と周りの人が気になるし。図書館など公共の施設は無料だけどいろいろ不便だし…。なんてあれこれ悩むならいっそのこと東京のような都会を離れて、環境のよい郊外にテレワークスペース完備のマイホームを建てちゃうというのはいかがでしょう。注文住宅なら住む人のライフスタイルや好みに合わせて自由に間取り等を決められます。
この記事では、これからマイホーム購入をお考えのあなたのための、注文住宅が引き渡されるまでの流れや所要期間などを解説します。快適なテレワークスペースを実現したい方は、ぜひ一度注文住宅を検討してみませんか?
実例を紹介!注文住宅だからできたテレワークライフ
テレワークに対応した家づくりは住宅メディアに掲載されることも増えてきましたが、まだまだ実際にどんな家ができあがるのかイメージしにくいかもしれません。ここでは注文住宅で新しいワークスタイルを実現させた例を紹介していきます。
注文住宅なら自分好みなテレワークスペースが実現
自宅でテレワークをするにあたり、パソコンを置く場所や集中できる環境などで困ったという声も多数聞かれます。家の一部を仕事場所に模様替えするよりも、設計段階からテレワークを目的としたワークスペースや書斎を作っておく方が、より自分にとって居心地の良い空間になります。 例えば、仕事の合間にちょっとした家事も片づけたい人には、キッチン横の空間をワークスペースに活用して行き来がしやすいように工夫。 少し狭めの空間が落ち着くという人には、玄関ホールの一部を仕切って机を置き、ブースのような個室を設計 毎日のように会議があるという人は、しっかりとした書斎に大きなモニターやマイク、照明などを導入して小さなスタジオのように整えておけば、いつでもオンラインミーティングに対応しやすいはずです。
通勤不要だから夕食の支度も家族みんなで
O市に注文住宅を新築したSさんファミリーは、注文住宅新築にあたりキッチンにはかなりこだわったとのこと。もともとは料理中でも旦那さんとお子さんがリビングでくつろぐ様子を見ていたいという奥様の要望によりオープンキッチンを設置しました。 ところが住み始めてみると、リモート勤務を終えた旦那さんも夕食作りに参加するように。今ではお子さんもお手伝いをして、家族みんなで食事を作るのが日課になっているそうです。仕事や家事ばかりの毎日から、家を建てたことで家族の時間が一日の中心に変わったのはうらやましいですよね。


休憩時間は子どもと遊んでリフレッシュ
T市に注文住宅を新築したTさんファミリーのお気に入りは、ウッドデッキ付きのお庭です。注目すべきは、旦那さんが在宅勤務のときにワークスペースとしてつかっているリビング内のカウンター。いつも家族を近くに感じながら、休憩時間にはお子さんと遊んでリフレッシュ。天気のいい日はウッドデッキでランチをしたり、お庭の芝生の上でボール遊びをしたり、植物に水をあげて成長を観察したり…。会社ではできない休憩時間の過ごし方が、仕事の充実感向上にもつながっているそうです。


建売住宅と注文住宅はココが違う
注文住宅の購入を検討する人がよく比較して選択に悩むのが建売住宅です。まずはそれぞれの特徴を簡単に知っておきましょう。
新築を見て決める「建売住宅」
「建売住宅」の特徴は、竣工(完成)済の新築住宅を実際に見てから購入できること。この場合、土地と建物は同時に購入することになります。もちろん成約後は短期間で入居が可能です。一方、これから建築する住宅のプランから判断して購入契約を結ぶ「売建住宅」もあります。「売建住宅」の場合、「これから建築する」といっても施工業者は指定されており、決められたプランの範囲内で希望を伝えていくことになります。
設計にイチからから関わる「注文住宅」
「注文住宅」の特徴は、自分の要望を設計に大きく反映できること。まずは施工業者と何度も打ち合わせを重ね、要望を盛り込んだ設計図や完成予想図を見て、納得できたら建築工事請負契約を結び、初めて建築工事が始まります。この場合、土地はあらかじめ用意しておく必要がありますが、富士住建であればご依頼主様が希望される住まいに最適な土地をお探しすることからトータルサポートが可能です。
注文住宅の良いところ
注文住宅のメリットは、構造や間取り、内装、設備などの自由度が高いこと。その分、建売住宅(売建住宅)よりも費用はかかりますが、自分のこだわりを形にしたオンリーワンのマイホームを実現できる喜びは、何物にも代えられません。 例えば、「長時間作業でも疲れにくい空間に」、「wi-fiがつながりやすく電源コードもスッキリするレイアウトに」、「オフィスの会議室とつないでも恥ずかしくないインテリアに」などのこだわりをカタチにできるのが注文住宅の最大の魅力です。 そのため建築会社を選ぶ際には、あなたのビジネスについて丁寧にヒアリングの上で設計を一緒に考えてもらえるような業者を探しましょう。
注文住宅の注意すべきところ
注文住宅の一番のデメリットはやはり費用です。希望を全部実現しようとすると際限なく費用がかかります。また自由度が高いといっても、構造強度に関わる部分や家事動線などの利便性、土地の建築基準などの理由で、希望通りにできない、または再考を勧められることもあります。そのため、最初に予算をしっかりと決め、その範囲内で優先順位をつけて要望を設計に盛り込んでいく必要があります。 自由度が高い分、施工業者との打ち合わせや契約などの手続きが多いという面もあります。マイホームにとことんこだわりたい人には良いですが、細かい部分はお任せしたいという人には時々煩わしく感じることがあるかもしれません。
注文住宅の引き渡しまでの流れ
注文住宅を建てようとすると、やるべきことがたくさんあるので、実際に入居するまでにどのような流れで進めていくべきなのかを事前に知っておくと安心です。
現収入・貯金を洗い出して予算を設定
住宅購入を検討するなら、必ず最初に予算設定からスタートしましょう。「貯金が●●円あるので、自己資金として出せるのはどのくらい?」「現在の収入が●●円だから毎月払えるのは…?」と現在の状況に合わせて、いくらまでなら住宅購入に割けるかを計算した額が予算になります。 計算が面倒に感じる方は、金融機関のサイトで借入シミュレーションが行えるサービスもありますし、不動産会社や建築会社の担当者にサポートしてもらうことも可能です。 ちなみに万が一、想定外の追加費用が必要になった場合のことも考慮して、最初は無理なく支払える金額に設定しておくと後々安心です。
まずは土地を確保しよう
「身内から譲り受けた土地がある」「建て替え」などの場合を除き、住宅用地は自分で確保しなければなりません。ネットなどから希望エリアを扱う不動産会社に問い合わせて、いくつかリストアップしてもらうか、ない場合は見つかり次第連絡してもらえるようにしましょう。また、土地探しにも対応できる富士住建のような建築会社であれば、相談窓口が一か所で済むので便利です。
家族で意見をまとめましょう
世帯主の理想だけを実現しても「家族みんながしあわせになる家」とは言えません。「趣味のためのスペースが欲しい」「家事を少しでもラクにしたい」など夫婦でまったく違う意見が出るでしょうし、「ベッドが置ける一人部屋がほしい」という子どもの意見、親も同居するようでしたら高齢者にとっての住みやすさも考慮する必要があります。一度は家族みんなの理想のマイホームや、今の生活で不便に感じているところをヒアリングして、家族みんなの意見としてまとめておくと、後で建築会社との打ち合わせがスムーズに進められます。
自分に合った建築会社を見極めよう
土地を確保できたら、設計施工を任せる建築会社の選定に入ります。CMなどで耳にしたことがある全国規模のハウスメーカー、地域事情に精通した地元の工務店、デザインセンスが魅力の設計事務所など、複数の業者から資料を取り寄せてみたり、住宅展示場やモデルハウス、ショールームがあれば見学に行くと良いでしょう。 自分の希望を形にできる工法を採用しているか?予算内で収まりそうか?担当者の人柄や相性は?さらにネットでのクチコミなど、じっくりと情報収集をしてから検討しましょう。 もちろん、建築会社や設計士から提案される間取りプランと見積り概算も依頼先選定の重要な要素です。 特に見積概算は内訳をよく見て諸経費などをしっかりと把握しておきしょう。一つひとつの金額が何のための費用なのか、理解できるまで説明を求めてください。また、業者ごとに細かく違うアフターサービスや保証制度などもよく比較することが大切です。 さらに可能であれば、建築中の現場を見せてもらうこともおすすめです。どんな現場監督や作業員に建築をお任せするのか、どんな意識で仕事に向き合っているのか、などを実際に見ておくと、選定の大きな決め手になるかもしれません。
住宅ローン事前審査と建築会社の決定
建築会社の選定を進めつつ、住宅ローンを利用する場合は早めに借入先の金融機関に事前審査を申し込んでおきましょう。 依頼する建築会社を絞り込み、間取り、建材、デザイン、見積りの修正、設備面の具体化、地盤改良工事の必要の有無など、細かい部分まで話を詰め、心から納得できたら依頼先との工事請負契約の締結となります。 締結時には「約款」、「設計図書」、「仕様書」、「見積書」、「間取り」の5種類の書類を受け取ります。この書類作成の費用や契約後のプラン変更が可能かなどは、契約前に確認しておくと安心です。
建築確認申請と住宅ローン本審査
「建築確認」とは、設計した建物や土地が建築基準法に適合しているかの確認のこと。これは契約した建築会社が、自治体または民間検査機関に必要書類を提出することになっていますので、担当者に任せておいて大丈夫です。ここで問題ないことを証明する「建築確認済証」が交付されて初めて、住宅ローンの本審査を受けることができ、通過すると借入先金融機関と契約となります。
いよいよ建築工事着工
いよいよ工事の着工ですが、工事中は重機などによる騒音が発生するため、着工前に近隣への挨拶まわりをしておくべきでしょう。この事前挨拶は現場監督などに任せることも可能です。また地鎮祭や上棟式を行うかどうかは、施工主(あなた)の意向で決めることができます。 建築中は進行状況を確認するため現場へ足を運ぶことをおすすめします。土台~骨組み~外観~内装…と次第にカタチになっていく様子や作業員の方々とのコミュニケーションが夢のマイホームへの想いを一層深いものにするはずです。
待ちに待った完成~引き渡し
竣工(完成)後は、再び自治体または民間評価機関による完了検査を受けます。建築確認申請の内容通りに建てられていると確認されると検査済証が発行されます。 最終的に、施工主(あなた)の立ち合いの下、プランとの相違や不具合の有無などのチェックが行われ、特に問題がないことを確認した後で正式な引き渡しとなります。
注文住宅を建てるための費用
注文住宅は、設計の自由度が高い分費用がかかることは前にも触れましたが、おおよそどのくらいの費用を見込んでおけばよいのでしょうか?
住宅の本体工事費
注文住宅購入費用の大半は本体工事費ですが、富士住建では 2,000~2,500万円が最も人気のある価格帯です。本体工事費とは文字通り建物本体にかかる費用の事で、基礎・躯体・屋根・内外装・設備などが該当します。昨今は社会的な事情により資材などの相場がよく変動しますので、あくまで参考程度にお考えください。
屋外給排水工事などは別途発生
本体工事の他に必ず発生するのは、屋外給排水工事です。具体的には、水道メーターから建物までの給排水工事、雨排水工事などがありますが、費用は敷地状況によって変動しますので忘れずに確認しましょう。照明、カーテン工事、冷暖房工事なども別途請求されることが多いです。ケースバイケースで地盤改良費や解体工事費が追加になることもあります。
建てた後は税金、保険、修繕費など
引き渡し・入居後も、不動産取得税(登記後1回)、固定資産税・都市計画税(毎年)、火災保険・地震保険などを支払うことになります。さらに、長く快適に住んでいくために建物の定期的なメンテナンスにかかる修繕費も重要です。外壁や屋根などの耐久年数に合わせて計画的に積み立てておきましょう。
注文住宅で失敗しないために
注文住宅の購入は、扱う金額が大きい上に、多くの人が初めての経験で大変な労力、さらに一定のルールやスケジュールもあり、建築の前後を問わずトラブルが起きやすいものです。「長年の夢だったはずの注文住宅で失敗した」とならないためにも、トラブルになりやすいポイントを押さえて、くれぐれも慎重に計画を進めましょう。
地盤調査してから施工業者と契約しましょう
土地の購入前に地盤調査をするためには売主の許可が必要となりますので、購入後に土地調査会社調査することが現実的です。しかし、地盤の状態が良くなく、思い描いた家が建てられないということもあります。後悔しないためにも、希望に沿った家が建てられることを確かめてから、建築会社と契約するようにしましょう。
ちなみに自治体で公開しているハザードマップから土地がどこに位置するかを参考に購入を検討することもある程度有効です。
値引きの要求には注意しましょう
家は非常に高い買い物であるがゆえ、少しでも安くなったらうれしいのは誰でも同じ。実際、建築会社の顧客担当者のほとんどは値引きの打診を受けています。しかし、業者によっては大幅な値引きにより契約を得たものの、その分を建築コストに転嫁するという事例もあります。建築資金が減れば、使える作業員や資材が限られてきます。作業員の数を減らし、少し安い資材を使われてしまった結果、質の悪い家が出来上がってしまう・・・というケースも。
富士住建では、利益率を最低限に抑えて値引きが1円もできない価格を「適正価格」とし、すべてのお客様、更に社員にも同一価格で、公平に提供させていただいております。設備メーカーとの年間契約により仕入れ単価を抑え、モデルハウスや豪華なカタログを作らないなど営業経費を削減し、その差額を会社の利益にするのではなく標準装備を充実させ、コストパフォーマンスの高い注文住宅「完全フル装備の家」を実現。一時的に会社のノルマを達成するための値引きキャンペーンなどで契約を急かすことは一切ありません。
詳細な見積書を精査した上で契約しましょう
注文住宅の業界では、「契約後に見積書よりも請求額が増えた!」という施工主の不満から担当者へのクレームに発展したという事例がしばしば聞かれます。またはクレームまではいかなくても見積以上の請求額になり支払いに困るということがないように注意が必要です。そのために詳しい見積書が提示されたら項目一つひとつをチェックし、設備のグレードが打ち合わせ内容と一致しているかを確認しましょう。また屋外給排水工事費や照明・冷暖房などの設備工事費、外構工事費など、本体工事費以外の費用を含む総額かどうかも確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐコツです。
イメージは、画像やイラストを使って共有しましょう
理想の住まいを具体的に伝えても、建築業者の担当者に正確に伝わっているかはわかりません。逆に担当者から設計図面を見せられても素人では要望が反映されているのか確信が持てませんよね?そんなコミュニケーションの食い違いが、完成後に「伝えたイメージと違う」というトラブルつながります。これを避けるためには「こんな風に欲しい」という要望は、口頭だけではなく、できるだけ近いイメージの画像やイラストを使って確実に伝え、同じイメージを共有しましょう。また、業者から提示される図面や完成予想図でわかりにくい部分があれば、写真やCG、立体模型などを使っての提案をしてもらえるのか確認しましょう。
この記事のまとめ
Point.1 まずは理想のワークスペースとは?を書き出してみましょう。
Point.2 土地探しは早めにスタートを!何事も余裕をもって進めましょう。
Point.3 問い合わせは積極的に!不明点は完全になくしましょう。
Point.4 支払いの金額と時期は何度もチェック!「総額」かどうかも確認しましょう。
Point.5 途中の気変わりはトラブルの元!要所要所で決断を固めましょう。
ほとんどの人が注文住宅を建てるのが初めてで、土地や設計、お金のことなど、わからないことばかりだと思います。だから、まずは建築会社や金融機関に資料請求をしたり、モデルハウスやショールームを見に行ってから注文住宅を検討してみると良いでしょう。
実際に計画が動き出してからも、不明な点は建築会社や金融機関の担当者に遠慮なくどんどん問い合わせをしましょう。
私たち富士住建は、「完全フル装備」&「自由設計」の家を「手の届く価格」で提供することを強みとしており、「住む人がしあわせになる」注文住宅のプランをご提案させていただきます。グループ内に不動産専門会社があることにより土地探しのサポートから対応でき、土地担当者と設計担当者が緊密に連携を取りながら希望される住まいの実現をお手伝いさせていただきます。
快適な在宅ワークができる住まいにご興味のある方は、お気軽に資料請求やショールームへお越しください。